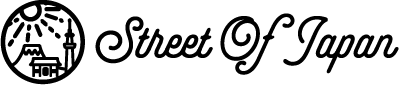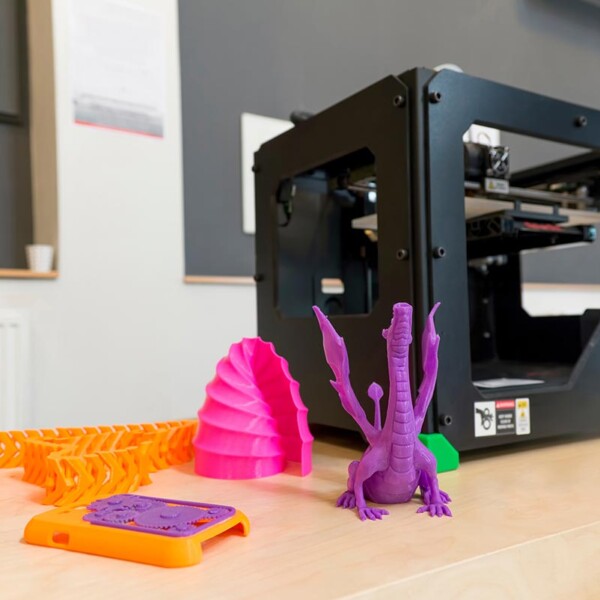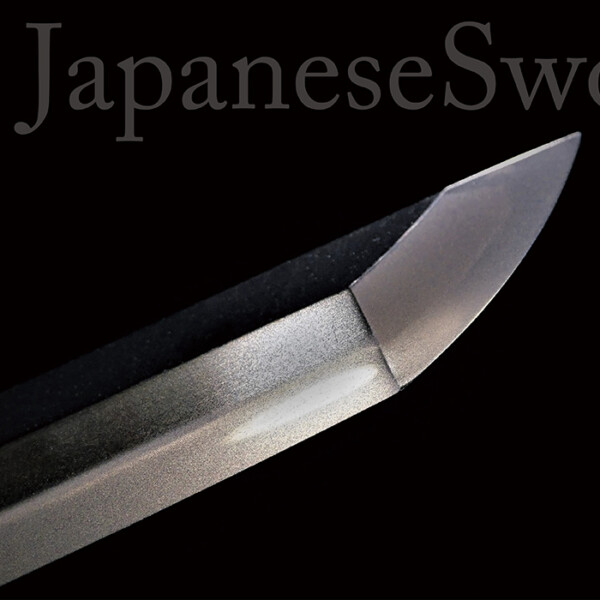ひさしぶりの牛丼。
先日、昼ご飯に何を食べようかと考えていたとき、ふと「牛丼が食べたい」と思った。
久しく食べていなかったが、なぜか無性に食べたくなったのだ。
ちょうど時間も限られていたし、手早く食べられる牛丼はぴったりだった。
そうと決まれば迷うことなく吉野家へ向かった。
店に入ると、カウンター席には仕事中らしきスーツ姿の人、作業着の人など、たくさん並んでいた。
牛丼屋のこの雰囲気、なんとも懐かしい。
注文した牛丼が運ばれてくると、その見た目と香りに一気に食欲がかき立てられる。
甘辛いタレが染み込んだ牛肉と玉ねぎ、それを受け止める白いご飯。
久しぶりに食べる牛丼は、思っていた以上に美味しく、どこか懐かしさすら感じる味だった。
食べ終わる頃にはすっかり満足していたが、同時に「牛丼っていつからこんなに日本人の生活に根付いたんだろう?」と気になった。

牛丼の歴史をたどると、明治時代にさかのぼる。
当時、文明開化とともに牛肉を使った「牛めし」が登場し、それが現在の牛丼の原型となったらしい。
吉野家はその草分け的存在で、創業は1899年(明治32年)。
「うまい、やすい、はやい」をモットーに発展し、全国に広がった。
確かに、今日も店に入ってから食べ終わるまで、わずか10分ほどだった気がする。
その後、牛丼チェーンとしては「すき家」や「松屋」も有名になった。
すき家はトッピングのバリエーションが豊富で、チーズ牛丼やキムチ牛丼などが人気だ。
一方、松屋は味噌汁が付くのが特徴で、牛丼のタレの味も少し濃いめな印象がある。
こうして比べてみると、それぞれの店に個性があり、「次は別の店の牛丼も食べ比べてみようかな」と思えてくる。
牛丼はシンプルな料理だが、それゆえに飽きがこない。
そして、食べたいと思ったときにすぐ食べられる気軽さが何よりありがたい。
きっと、またある日突然「牛丼が食べたい」と思う日が来るだろう。
そのときは、また迷わず牛丼屋の暖簾をくぐることになるに違いない。
Profile

-
PEACE CITY に住んでおります。
アウトドアブームが落ち着いた今、
ボタニカルブームに足を踏み入れようとしています。
Latest entries
 Food2026.01.16夏の日本、アイスの季節
Food2026.01.16夏の日本、アイスの季節 Lifestyle2025.12.1927年モノのエアコンからの解放
Lifestyle2025.12.1927年モノのエアコンからの解放 Travel2025.11.17世界遺産 「宮島」
Travel2025.11.17世界遺産 「宮島」 Lifestyle2025.10.17春の風物詩
Lifestyle2025.10.17春の風物詩