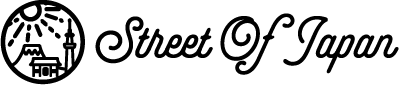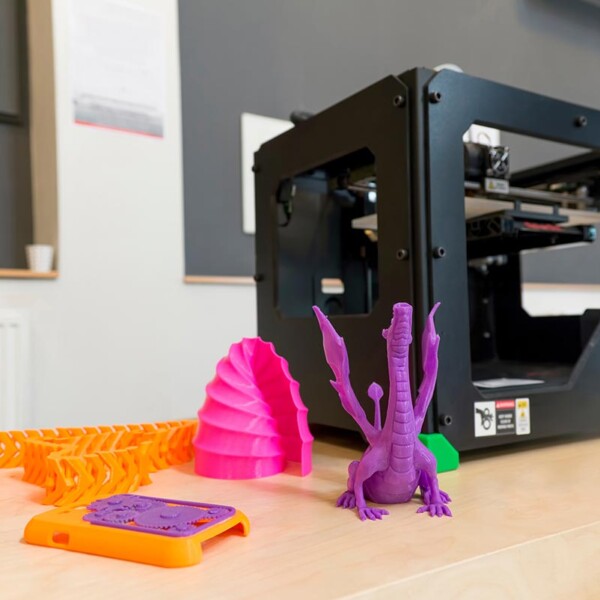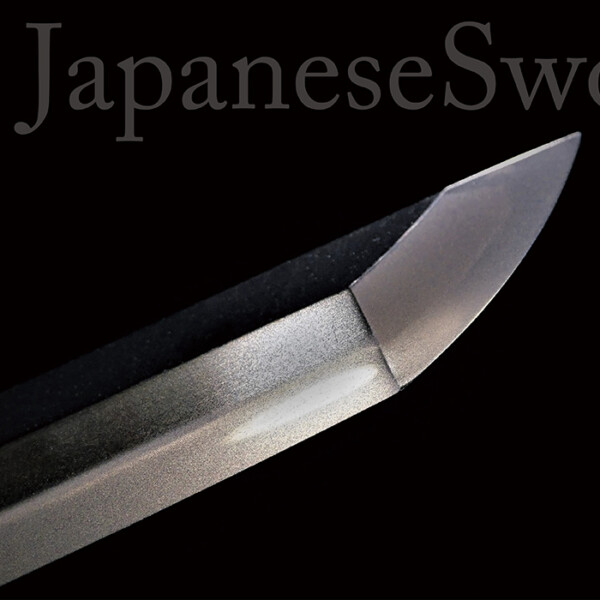節分、豆まきと鬼について考える
日本には春夏秋冬と四季があり、季節の変わり目で立春、立夏、立秋、立冬のそれぞれ前日を節分と呼ぶのだが、現在(江戸時代頃から)では立春の前日だけが節分とされているそうです。
さて、毎年2月3日が節分だと思っていたのだが、今年はなぜか2月2日が節分で、はて、何でだろうと思ったのは私だけだろうか?ニュースでも取り上げていたが4年に一度の閏年(地球が太陽を一年かけて一周する際に生じる時間的なズレの調整)よりさらに微調整する必要があるらしく・・・、ちょっといろいろ調べてみたのだが、天文学的に難しい話にたどり着いたのでここでは詳しく話しません。興味ある方は調べてみてください。なので今年の立春は2月3日、節分が前日の2日だそうです。
そんな訳で今年の節分は2月2日。様々な行事が日本各地で執り行われたようだが、最も有名なのが「豆まき」である。季節の変わり目に起こる病気や災害などを鬼に見立てて邪鬼を追い払う儀式が日本各地に広まったものだ。

もう何年も前の話だが、我が家の子供たちが幼少の頃、父親が鬼の役になりお面をかぶり「鬼は外!」「福は内!」と叫びながら豆を投げつけられる、どこの家庭でも行われたことであろう。そういえば一番下の子が保育園に通っていた頃、豆まきの行事が園の三代名物の一つで、それはもう本格的な鬼が登場し、秋田のなまはげを思わせるような見事な変装を保育士(保母さん)数人が演じ園内を暴れ回る、子供たちは大泣きし園内を逃げ回っていたのだが、今もあの保育園でやっているのだろうか?懐かしい思い出だ。
地方によって様々な掛け声があるようだ。
「福は内、鬼は外」が一般的だと思うが・・・
・群馬県藤岡市鬼石地区→「福は内、鬼は内」
・宮城県村田町→「鬼は内、福も内」
・東北各地→「福は内、鬼は外、鬼の目ん玉ぶっつぶせ」 過激だ!!
などなど・・・。

豆まきの豆は・・・何をまく???
私が子供の頃は袋で買ってきた大豆(煎り大豆)をばらまいたものだが、最近は様々のものがあるようで、落花生だったり、後片付けを考え散らからないように小袋入りの大豆(袋ごとまく)だったり、柿の種や豆菓子など、時代の移り変わりで様々なものへ変化しているようだ。


ニュースで聞いた話
渡辺さんの家では「豆まき」はしない・・・、という話を報道番組で見た。実際に渡辺姓の数人にインタビューをしていたが、本当に豆まきはしないと答えていた。なんでも平安時代に「渡辺綱(わたなべのつな)」という武士が鬼退治をして鬼が寄り付かなくなったという言い伝えから渡辺さんの家では豆を巻く必要がないらしい(笑)。渡辺綱は昔話の桃太郎だという説もあるらしい。
まぁ近々、会社に渡辺さんがいるので豆まきについて聞いてみようかと思う。

おまけ・・・恵方巻とは?
ここ数年、節分=豆まきよりも、節分=恵方巻のほうが何かと話題で出てくる気がします。もともとは古代中国の風習で、節分に恵方を向いて特定の食物を食べることで厄払いや福を招くといった信仰がつたわり江戸時代に恵方巻を食べる習慣になったということだが。ただ、恵方巻は私が子供の頃は全く食べたことがなく存在すら知らなかったのに、我が家ではここ数年、節分当日の食卓には必ず恵方巻が出てくるが、 節分に恵方巻の習慣は、どうもしっくりこないのは私だけであろうか?
Profile

-
神奈川県横浜市生まれの生粋の浜っ子。初老を迎えたゴルフ大好き人間です!
あと何年ゴルフができるか?
飛距離の維持と技術向上、競技ゴルフ出場を目指し、日々奮闘中。
他の趣味:庭いじり、声を出して歌う事、野球観戦・・・など。
Latest entries
 Lifestyle2025.12.03我が家の庭は猫の額ほど・・・。Part-9「紫陽花(あじさい)と梅雨」
Lifestyle2025.12.03我が家の庭は猫の額ほど・・・。Part-9「紫陽花(あじさい)と梅雨」 Travel2025.11.05日本人は富士山が大好き
Travel2025.11.05日本人は富士山が大好き Lifestyle2025.10.03日本人はお風呂好き!! スーパー銭湯のお話し
Lifestyle2025.10.03日本人はお風呂好き!! スーパー銭湯のお話し Travel2025.08.22お花見シーズン到来!! 伊豆半島花見ドライブと絶品パフェ
Travel2025.08.22お花見シーズン到来!! 伊豆半島花見ドライブと絶品パフェ