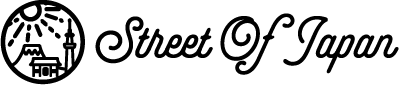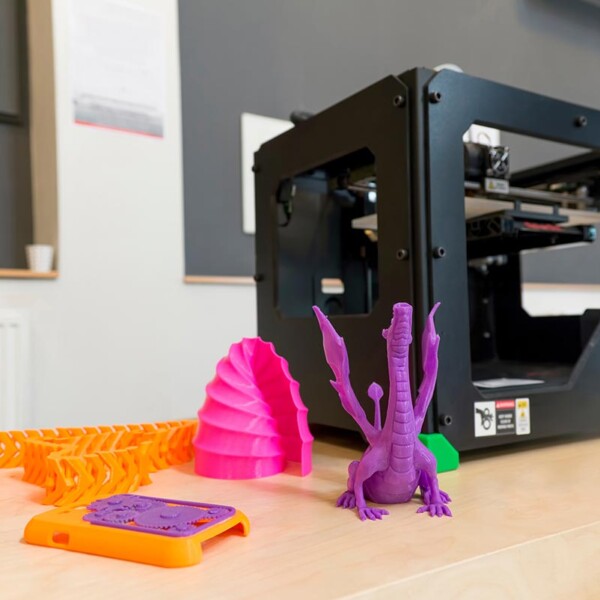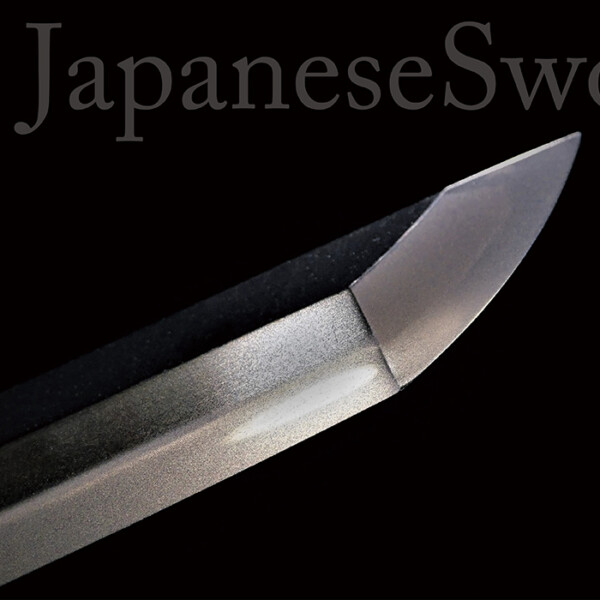日本人の伝統行事「七五三」について
七五三(しちごさん)は、子供の成長を祝う日本の伝統行事です。
7歳、5歳、3歳の子供たちが対象で、11月15日に神社に参拝し健やかな成長を願います。
七五三は諸説ありますが平安時代(A.D.794〜1180年)から続く風習とされ、長い歴史があります。
● 七五三の由来と歴史
七五三の由来には諸説ありますが、平安時代の貴族や武士の間で行われていた成長儀式にあるとされています。
現代に比べて医療の発達が未熟で衛生面もよくなかった昔は、子供が無事に育つことが難しく、特に7歳までの死亡率がとても高く、成長する節目で神様に感謝し無事を祈る風習が生まれました。
やがて江戸時代に現在の七五三の原型として武家や商人の間に広まったといわれています。
11月15日が七五三の日に定められた理由については諸説ありますが、収穫の終わりにあたる時期で神様に感謝を捧げる「神迎え」の時期と重なることからとも言われています。
● 年齢ごとの意味
七五三は、地域によって独自に発展した側面もあり、少しずつ文化が違う場合もあります。起源となった儀式は以下の3つです。
・3歳(髪置きの儀)
平安時代の頃は男女ともに生後7日目に頭髪を剃り、3歳頃までは丸坊主で育てるという風習がありました。これは頭を清潔に保つことで病気の予防になり、のちに健康な髪が生えてくると信じられていたためです。
そして、3歳になると髪を伸ばし始めました。
これを「髪置きの儀」といい、3歳を迎えた子供が無事に成長し、髪を伸ばせるほど健康であることを祝う儀式です。
・5歳(袴着の儀)
平安時代には5~7歳の頃に、当時の正装である袴を初めて身に付ける「袴着(はかまぎ)の儀」を執り行いました。別名「着袴(ちゃっこ)」ともいわれるこの儀式を経て男の子は少年の仲間入りをし、羽織袴を身に付けたとされています。
現代でも、5歳の男の子が袴や羽織を着て神社に参拝し、成長を祝います。
・7歳(帯解きの儀)
女の子は7歳になると、それまでの紐付きの着物から、帯を締める本格的な着物を着るようになりました。これを「帯解きの儀」といい、成長し、女性としての一歩を踏み出すことを表しています。
現在でも、7歳の女の子は華やかな着物を着て神社に参拝し、成長を祝います。

● 七五三の習慣
七五三の儀式では、お子さまの成長を感謝するため神社に参拝に行きます。
一般的にはその土地を守ってくださる神様(氏神様)がいらっしゃる近所の神社へお参りに行くのがしきたりです。
参拝の後は、家族で写真撮影をしたり、食事会を開いたりすることが一般的です。
また、七五三の祝いには「千歳飴(ちとせあめ)」が欠かせません。
千歳飴は細長い形をしており、長寿と健康を願う縁起物とされています。
袋には「鶴」や「亀」などの縁起の良い動物が描かれており、これもまた子供の健康や長寿を祈る意味が込められています。

● 現代の七五三の祝い方
現在の七五三では、伝統を尊重しながらも現代のライフスタイルに合わせた祝い方が多く見られます。
特に着物をレンタルしたり、写真スタジオで記念撮影をしたりすることが一般的です。
多くの神社や写真スタジオでは、七五三のシーズンに合わせたプランが用意されており、家族での思い出作りがしやすくなっています。
11月15日が平日の場合には、その前後の土日や祝日にお祝いする家庭も多く、混雑を避けるために前倒しして、10月中旬から11月頭にかけて参拝する方も多くいます。
一昔前と比べると、七五三の時期や年齢については自由度が高くなっているので、撮影や参拝の時期は、各ご家庭に合わせ柔軟に変更しても問題なく、また、もともと女の子は3歳と7歳、男の子は3歳と5歳(5歳のみの地域もあり)でお祝いをしていましたが、最近は性別問わずすべての年齢でお祝いをする、兄弟の年齢に合わせ5歳の女の子や7歳の男の子もお祝いをするという方も増えています。
● まとめ
七五三は、子供たちの健やかな成長を祝う大切な行事です。
平安時代から続くこの風習は、時代を超えて親から子へと受け継がれており、家族の絆を深める大切な機会です。
Profile
- グラフィックデザインやweb、ディレクションも対応するデザイナーです。
Latest entries
 Lifestyle2025.12.26日本の四季を彩る12ヶ月の花
Lifestyle2025.12.26日本の四季を彩る12ヶ月の花 Lifestyle2025.11.21日本のお祭り「花火大会」について
Lifestyle2025.11.21日本のお祭り「花火大会」について Lifestyle2025.10.22日本の「母の日」について
Lifestyle2025.10.22日本の「母の日」について Lifestyle2025.08.15日本の「ひな祭り」について
Lifestyle2025.08.15日本の「ひな祭り」について