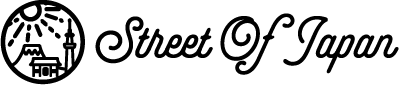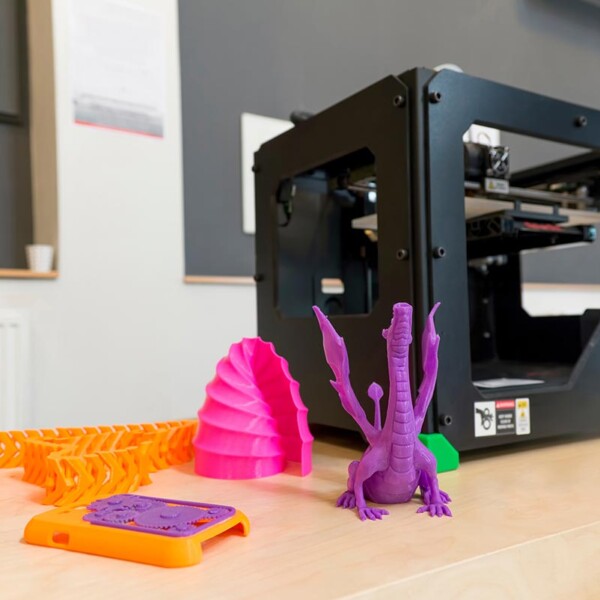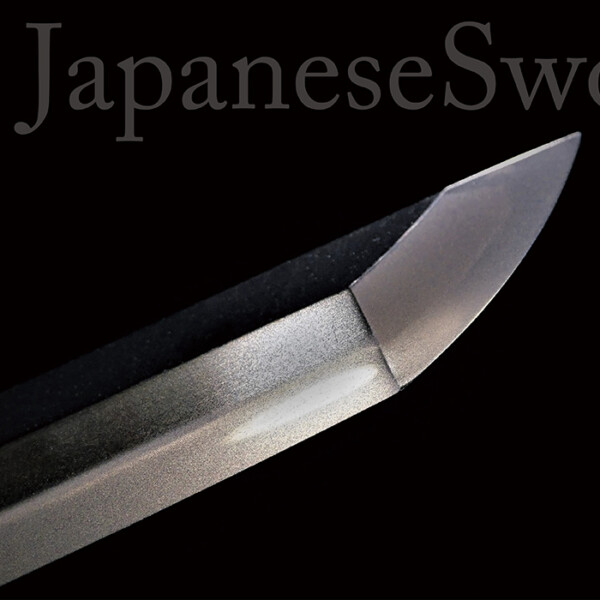夏休みの自由研究
暑い夏の日、駅のホームでベンチに座って電車を待っていると足下にアリが近づいてきました。今にもスニーカーの上に登ってきそうな勢いです。
アリを見ていると、いつも小学生の頃の夏休みを思い出します。
日本の小学生が抱える悩みの一つとして、夏休みの自由研究があるのではないでしょうか。
わたし自身もそうでした。「夏休みは最高!楽しい!」と歓喜している頭の片隅に何かモヤモヤしたものがある。自由研究というのは、わたしにとってそんな感じの立ち位置でした。
今の時代はわからないのですが、わたしの時代/学校では、自分で何かテーマを考えてそれを大きな紙(模造紙)にマジックで文章やイラストを書いて情報を整理してまとめる。そして、それをクラス全員の前で生徒たちが順番に発表していく。というもので、たしか写真を貼っていた同級生もいたと思います。これがとても苦手で苦手で苦手で仕方なかったんです。その時の記憶はほとんど残ってないのですが、ひとつだけ覚えている自分の研究として「アリについて調べる。」というものがありました。

それは、今思えば、なんとも恥ずかしいのですが「アリは甘いものが好きなのか?」ということをテーマに、家の庭に砂糖を置いて、そこにアリがやってくるかどうか?というような簡単な研究内容でした。あまりに題材が見つからず、きっと苦肉の策だったのでしょう。
研究の結果は察しの通りで「アリは砂糖に向かって移動してくる。」という誰でも予測がつくもので、その時の成績は覚えてませんが、ずいぶん最近まで「なんで、あんな研究をしてしまったのだろう。。」と考えたりすることもありました。もっと別の研究があったんじゃないかと。
でも、最近はちょっとだけ考え方が変わって、当時の見え方も変化してきたんです。
つまり、この「アリは甘いものが好きなの?」という調査は、世間的には「常識」「当たり前」と言われていることを疑って自分で再確認/検証した。という見方もできなくはないからです。(少し強引ですが)
今の時代、「誰々や、世間が言ってるから。」とか「とても分かりやすい説明だし、なんか良さそう!」というような理由で納得するのはちょっと違う気がします。
「みんなは、そう言ってるけど本当?」という物事への態度を持つことが大事な気がするのです。
「まあ、そうかもしれないけど、一応調べさせて」とか「ちょっと待って。考えさせて。」というような感じです。それに、自分で調べたり考えたりするとなんか気分がよい。
もちろん、小学生の頃の自分は、そんなことは考えてもいなかったわけですが、もし、子供時代の自分に会うことがあったら「なかなか良い着眼点を持ってると思うよ。めげるなよ。」と声をかけたいなって思います。
なんだか、やっと自由研究が終わった気がします。