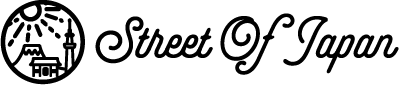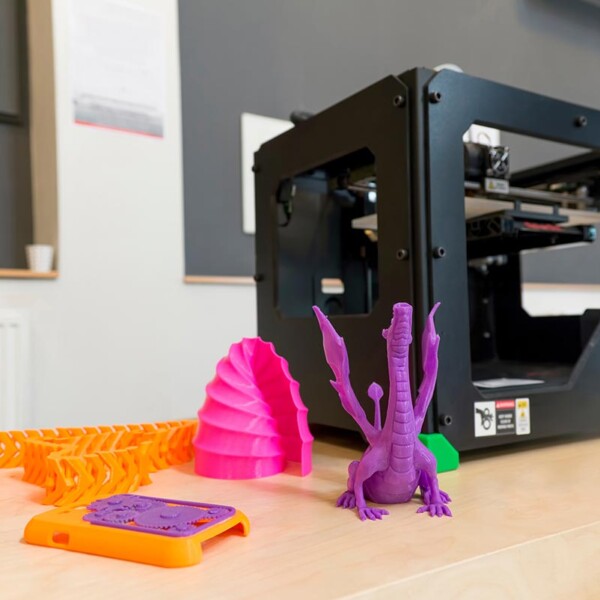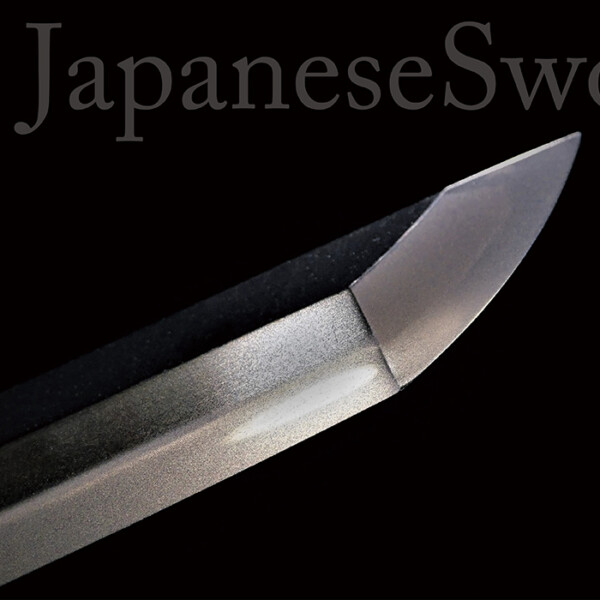三月のイベント「春の彼岸」
三月のイベントに「春のお彼岸(ひがん)」があります。
「お彼岸」って日本人でも耳なじみはあるけど、説明するには難しい言葉のひとつです。
そこで、インドネシアの方々が日本人でも説明するのが難しい「お彼岸」を知っていれば日本人に一目置かれること間違いなしです。
そこで、今回は「お彼岸」について調べた内容をお伝えしようと思います。

お彼岸は、毎年 春と秋の2回 行われる、日本独特の伝統行事です。でも、これはただの「お墓参りのイベント」ではありません。実は仏教の教えに深く関係していて、ちょっと神秘的な意味があるんようです。インドネシアの文化とも意外な共通点があるかもしれませんの、ぜひ楽しんでください!
お彼岸は 春分の日(3月頃)と秋分の日(9月頃) を中心に、前後3日間を合わせた 7日間 に行われます。この時期、日本の多くの人が お墓参り をして、ご先祖様に感謝を伝えます。
でも、なぜこの時期なのか?それは 太陽の位置 が関係しています。春分と秋分の日は、昼と夜の長さが同じになる日です。この日は、太陽がちょうど真西に沈みます。
仏教では、西の彼方に「極楽浄土(ごくらくじょうど)」という、亡くなった人が行く世界があると考えられています。西方に沈む太陽を礼拝し、遙か彼方の極楽浄土に思いをはせたのが彼岸の始まりの様です。
インドネシアにも「スラマタン(Selamatan)」のような、ご先祖を敬う儀式がありますよね?お彼岸も、それと同じように「先祖を大切にする心」が込められています。
日本では主に お墓参りをして、ご先祖に感謝する という形になっています。
日本のお祭りには、特別な食べ物がつきものです。お彼岸では 「ぼたもち」 や 「おはぎ」 という甘いお餅を食べます。

実は、春のお彼岸では「ぼたもち」、秋のお彼岸では「おはぎ」と名前が変わるだけで、ほとんど同じです。違う点は、春は「牡丹(ぼたん)」の花にちなんで「ぼたもち」、秋は「萩(はぎ)」の花にちなんで「おはぎ」と呼ぶこと以外、あんの種類が「ぼたもち」はこしあん、「おはぎ」は粒あんを使用などあるようです。
そして、なぜお彼岸にこの甘いお餅を食べるのかというと、それはあんの原料の 小豆(あずき)の力!昔の日本では、赤い色には 魔除けの力 があると信じられていました。そのため、先祖の霊を守りながら自分たちも元気でいられるように、小豆の餅を食べるようになったのです。
また、お彼岸の時期には「ご先祖の霊が家に帰ってくる」と考える人もいて、家の掃除をしたり、お供え物をしたりします。
お彼岸は、日本独特の行事ですが、ご先祖様を大切にする心や、家族が集まる時間を大切にするという点で、インドネシアの文化ともつながる部分があります。
昼と夜の長さが同じになる春分・秋分の日に、お墓参りをしたり、ぼたもちを食べたりすることで、日本人は亡くなった人と心を通わせてきました。インドネシアの皆さんも、日本に来る機会があれば、ぜひお彼岸の雰囲気を体験してみてください!
Profile

-
三大栄養素は、運動/音楽/お酒
欲しいものは、ファッションセンスと年甲斐
お笑い芸人にいそうな顔とよく言われます。
Latest entries
 Sports2026.01.21東京マラソンのお金の色々
Sports2026.01.21東京マラソンのお金の色々 Lifestyle2025.12.22七夕の織姫と彦星の本音を考えてみる
Lifestyle2025.12.22七夕の織姫と彦星の本音を考えてみる Sports2025.11.19日本の人気マラソン大会とは?ランナー目線でご紹介!
Sports2025.11.19日本の人気マラソン大会とは?ランナー目線でご紹介! Food2025.10.20抹茶と緑茶
Food2025.10.20抹茶と緑茶